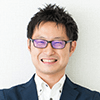「子供は欲しいけど、派遣社員として産休や育児休暇が取れるのか心配・・・」
とお悩みではありませんか?
この記事では、派遣社員の育児休暇や産休について解説します。みなさんの仕事と育児の両立のお役に立てば幸いです。
派遣会社おすすめランキング【元派遣会社】が評判や口コミを紹介
目次
派遣社員はそもそも産休・育休を取得できる?
派遣社員といっても、会社が異なれば働き方も変わってくるため、「3ヶ月更新の派遣社員も産休や育休を取得できる?」や、「社会保険加入から1年以上経過していないとだめ?」などの質問が多く寄せられます。
派遣社員はどのような条件を満たしていれば産休を取れるのか把握して、自分に当てはまるのか確認してみましょう。
ここからは、派遣社員を「有期雇用派遣」と「無期雇用派遣」の2つの雇用区分に分けて、それぞれで産休・育休を取得できる条件について解説します。
「有期雇用派遣」産休・育休を取得するための条件
契約に限りのある「有期雇用派遣」の派遣社員が、産休と育休を取得するための取得条件についてそれぞれ解説していきます。
短期契約であっても、条件を満たしさえすれば手当なども取得できるようになるでしょう。
有期雇用派遣が「産休」を取るための条件
産休は、「産前休暇」と「産後休暇」の両方を意味します。出産予定日の6週間前から休暇を取る産前休暇と、出産日の翌日から8週間の休みとなる産後休暇を取ることになります。
産休は派遣社員であっても、会社側は産休を求められたら就業させてはならないと、労働基準法で定められています。
産後休暇は、産後8週間取得することができますが、必ずしも8週間取得しなければならないわけではありません。
労働基準法題65条2項にあるように、医師が支障がないと認めた場合は、産後6週間を経過すると復職することができます。これは、勤務形態が正社員であっても、派遣社員であっても同様になります。
産前産後(第65条)
1.6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(※1)の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。
2.産後8週間(※2)を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。
引用元:厚生労働省愛媛労働局「労働基準法のポイント| 産前産後(第65条) 育児時間(第67条)生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条)就業規則の作成・変更・届出の義務(第89条~第92条)」
有期雇用派遣が「育休」を取るための条件
有期雇用契約の派遣が育休を取るためには、以下の条件が必要です。
- 同じ派遣元会社で1年以上の勤務(派遣先が異なる場合も認められます)
- 週の所定労働日数が3日以上(週2日以内のケースは会社に断る権利があります)
- 育休開始日前の2年間に、1ヶ月の出勤が11日以上の形が12ヶ月以上続いたこと(失業保険給付がされた場合を除き、前職と通算可能です)
- お子さんが1歳6ヶ月を迎えるまでに契約の終了が確定していないこと
つまり、同じ派遣元の会社との間で「雇用期間が1年以上あること」が要件となりますので、派遣先が変更になった場合であっても、原則としては育休の取得は可能です。
なお、新しい派遣先が決まる前に育休を取得するとなる場合などにおいては、派遣元会社からの不利益取扱を受けないように注意する必要があります。
「無期雇用派遣」が産休・育休を取得するための条件
無期雇用派遣として産休や育児休暇を取得する場合は、有期雇用派遣と異なる部分もあるため、それぞれの条件を紹介していきます。
無期雇用で働いている方または、目指す方は条件をしっかりとチェックしておきましょう。
無期雇用派遣が「産休」を取るための条件
無期雇用派遣で産休を取得できる条件は、有期雇用派遣の育児休暇と同じ内容になります。
育休については様々な条件がありますが、産休を取ることは母子の健康を守ることにつながるため、なくてはならない休暇のひとつです。
無期雇用派遣が「育休」を取るための条件
無期雇用の派遣社員が育休を取るための条件は、次のようになっています。
- 同一の派遣元会社で1年以上の勤務(派遣先が異なる場合も認められます)
- 週の所定労働日数が3日以上(週2日以内のケースは会社に断る権利があります)
- 育休開始日前の2年間に、1ヶ月の出勤が11日以上の形が12ヶ月以上続いたこと(失業保険給付がされた場合を除き、前職と通算可能です)
有期雇用派遣では「お子さんが1歳6ヶ月を迎えるまでに契約の終了が確定しない」という条件がありますが、無期雇用派遣ではこの条件を除いた3つの項目を満たしていれば育休を取得する権利が与えられます。
派遣会社によって細かい違いもあるため、必ず確認しておくようにしましょう。
派遣社員が育休・産休を取るために必要な手続き
派遣社員が産休と育休を取るために必要となる手続きについてまとめました。
条件を満たして正しい手順を踏めば、誰でも産休と育休を取得する権利を持っています。
産休の手続き
産休を取得するためにはまず、以下の点を決めることが必要です。
- 派遣会社に妊娠の報告を行う
- 出産や育児で利用できる給付金や制度を確認する
- 妊娠中の働き方について相談して決める
その後、産休中に社会保険の免除を行ってもらうために産前産後休業取得者申出書を、年金事務所に提出することになります。
予定より早く産休が終わった時は、年金事務所に「産前産後休業取得者終了書」を提出することになります。
育休の手続き
育児休暇についても派遣会社に相談した後に、年金事務所へ「育児休業等取得者申出書」の提出を行えば、社会保険の免除が受けられます。
産休中と同じく、予定よりも早く育休が終わる場合は、育児休業等取得者終了書を提出する必要があります。
派遣社員がもらえる育休と産休の手当はいくら?
派遣社員が育休や産休を取った際にも、一定条件を満たしていれば手当を受け取れます。
産休の手当
産休の手当には、以下の2つがあります。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
それぞれがどんな手当で、いくらもらえるのかお伝えします。
1.出産育児一時金
出産育児一時金は、一児につき50万円の支給を受けられます。
出産育児一時金が得られる条件は、以下のいずれかを満たしていれば誰でも取得できるようになっています。
- 派遣会社の健康保険に加入していること
- ご主人の健康保険の扶養となっていること
- 国民健康保険(国保)に加入していること
※ただし、健康保険の被扶養者として支給される場合は、「家族出産育児一時金」と名称が変わります。
2.出産手当金
出産手当金は、産前6週間から産後8週間までの給料が支払われない場合に、標準報酬月額を30で除して得た額(=標準報酬日額)の3分の2相当額の給付が受けられます。
条件としては、以下の条件があります。
- 健康保険の被保険者であること
- 出産日以前42日から出産日後56日までの期間内で、労務に服さなかった期間があること
これは、育児休業を取得させるための要件として「育児介護休業法」で規定されている要件であり、派遣労働者であっても、所属している派遣会社の健康保険の被保険者として加入していれば受給は可能です。
しかしながら派遣会社の社会保険に自分自身が加入していることが条件となるため、国民健康保険やご主人の健康保険の扶養になっている場合は、受給できない点にはご注意ください。
育休の手当
育休の手当には、子どもが1歳になるまで、または支給対象期間を延長した場合は1歳6ヶ月または2歳まで受けられる育児休業給付金があります。
派遣社員が、育児休業給付金を受給できる要件は、雇用契約が「有期雇用労働者」か「無期雇用労働者」かで若干異なります。
どちらの雇用契約でも、育児休業を開始した日の前2年間に被保険者期間が12か月(育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。)以上あることが必要になります。
「有期雇用労働者」の場合は、育児休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないことが追加で必要とされます。
育児休業給付金の支給額
育児休業給付金は、休業期間によって支給割合が変化します。
育児休業給付金の支給に関連づける休業日数が通算して、
180日に達するまでの期間は、休業開始時賃金日額(育児休業を開始した日に退職したものと仮定した場合における基本手当(失業手当)の1日当たりの金額)の67/100相当が支給されます。
181日以降については、50/100相当額に支給割合が変化します。
派遣会社への申請が必要となるため、事前に派遣会社の担当と相談しておくといいでしょう。
妊娠後の復帰はすぐできる?
妊娠後には8週間の休みが必要とされていますが、さらに早く復帰することはできるのでしょうか?
産休日を短縮する方法について紹介します。できるだけ早く復帰したいという方におすすめです。
産休を短縮できる条件
いくら本人が働きたいという意識があっても、会社側にはスタッフの健康と安全を守る義務があります。
そのため産休期間を短縮する条件として、医師の同意がなければなりません。
産後6週間を経過した女性から請求があり、なおかつ医師が支障がないと認める業務であれば就業することが可能です。
子供の預け入れ先が決まらない場合はどうなるの?
育児休暇を終えても、保育所などのお子さんの預け入れ先が決まらなかった場合は、お子さんが1歳6ヶ月もしくは、2歳になるまで延長できるケースもあります。
ただし、以下の期限までに保育が行えない状態を証明できる書類の提出と、申請を行わなければなりません。
- 1歳6ヶ月までの延長をするためには1歳の誕生日の2週間前までに
- 2歳までの延長は1歳6ヶ月を迎える2週間前までに
派遣社員の産休は延長できる?
産休期間の延長については、医師から期間以上の休暇や、入院が必要と指導を受けた場合は、派遣会社にしっかりと処置を取ってもらえるように申請しましょう。
また双子妊娠の場合は、14週間前から産前休暇を申請できます。
産休中に契約期間満了を迎えたらどうなる?
産休中に契約終了(満了)を迎えたり、個人単位の抵触日を迎えたりしても、以前から契約更新または、新たな契約を行うことが決まっていれば、そのまま契約が更新されずに終わるということは通常ありえません。
個人単位の抵触日とは、同一組織の勤務が上限3年まであり、その期限日のことを指します。
ただし産休に理解や馴染みがない会社も残念ながらあるようなので、産休や育休について明記されている派遣会社に登録するようにしましょう。
派遣の抵触日については、こちらの記事でより詳しく解説しています。興味のある方はぜひご一読ください。
 【派遣のプロが教える】派遣の抵触日ってなに?「3年ルール」と言われる理由は?
【派遣のプロが教える】派遣の抵触日ってなに?「3年ルール」と言われる理由は?育休明けにすぐに退職するのはまずい?
育休明けにすぐ辞めたりするのは、法律上で違法となることはありませんが、育休とは本来仕事に復帰するための方法なので、育休明けにすぐ退職することはあまりおすすめできません。
精神的に疲れてしまったり、物理的に仕事を継続することが困難になったりする場合の退職は問題ありません。
ですが、育休で手当をもらった直後の退職になってしまうと、道義的に問題があると思われてしまうリスクがあります。
育休明けは可能な限り、仕事を続けていくことを目指していきましょう。
産休に入る前の挨拶って必要?
派遣先に産休に入ってしまう前の挨拶は強制ではありませんが、産休期間の間、代わりに仕事を行ってくれるスタッフもいるため、挨拶はマナーとしてした方がいいでしょう。
みんなの前で挨拶する場合(朝礼や終礼などの例文)
お疲れ様です。〇〇部署の「フルネーム」です。
私事ではありますが、 〇月〇日より、産休に入らせていただくことになりました。
その間の業務については〇〇さんに引き継いでいただくことになりました。(はっきりと決まっていれば)
妊娠中の間も皆様にはご配慮をいただき、誠にありがとうございました。
また産休後には、育児休暇に入る予定となっておりますので、〇〇年〇月頃の復帰になるかと思います。
その際にはまた皆さんとお仕事をしていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
挨拶メールの場合(社内メール、取引先メール簡単なひな形)
社内メールの挨拶
お疲れ様です。「フルネーム」です。
また私事になりますが、 〇月〇日より産休をいただくことになりました 。
休暇中の業務につきましては〇〇さんに行なっていただきます。
在籍中は皆様に大変お世話になり、本当に感謝しております。
不在になってしまう期間は、皆様にご迷惑をおかけしてしまうことになり、申し訳ございません。
復帰は〇〇年〇月頃を予定しております。
メールで挨拶する形となってしまい大変恐縮ではありますが、 再び一緒に働かせていただければ幸いに存じます。
社外メールの挨拶
いつもお世話になっております。
〇〇会社の「フルネーム」です。
私事となり大変恐縮ではございますが、この度子供を授かることとなりました。
つきましては〇年〇月より産休をとらせて頂きます。
お手数をかけることになって申し訳ございませんが、産休中は〇〇が担当させていただきます。
復帰の際はご挨拶させていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。
どのシーンで挨拶する際にも、自分が長期の休みを取ってしまうことに関して申し訳なく思っている気持ちと、感謝を忘れずに復帰を前提とする前向きな内容となるようにしましょう。
菓子折りは必要?予算はどれくらい?
産休へ入る前の菓子折りを送る際は、一個あたり70円から200円くらいの予算がちょうどいいとされています。
あまり高級すぎるお菓子を準備すると、逆に気を遣わせてしまったり、次に産休を迎えるスタッフにプレッシャーをかけることになりかねません。
特別お世話になった方などがいれば、みんなに配る分とは別に数100円のお菓子を用意する方法もおすすめです。
菓子折りは必要というわけではありませんが、自分が抜ける部分をサポートしてくれるスタッフに、感謝の気持ちを形として伝えてみてはいかがでしょうか。
派遣社員が産休を取るメリット・デメリット
派遣社員が産休を取る際にえられるメリットはあるのか、逆にデメリットとなってしまう部分はどこなのか、それぞれ紹介します。
産休のメリット
産休をとって休暇を得られれば、派遣先との契約を切らずに出産と子育てに集中できるポイントが大きなメリットとなるでしょう。
仕事を辞めてしまっては、産休復帰後にまた新しい職場を探さなければならず、もし見つかったとしても、慣れない職場でストレスを抱えてしまうかもしれません。
そうならない為にも、産休をうまく活用して慣れ親しんだ職場で復帰した方が、精神的にも安心して業務に戻れるのではないでしょうか。
産休のデメリット
産休を取ることのデメリットは、同じ職場に復帰できない可能性もあるという点です。
派遣先によっては、自分の代替で入っていた派遣社員とそのまま契約を結びたいと言ってきたり、求人そのものがなくなってしまったりすることも考えられます。
産休中にそのようなことが起きてしまうと対応しきれず、産休を終えた頃には新しい派遣先を探さなければならないといったこともあるかもしれません。
大手派遣会社であれば対応してもらえますが、産休への対応が充実していない会社もあるため、サポート体制も含めて確認しておきましょう。
男性派遣社員も育休取得はできる?
育児休暇の取得は、男女関係なく申請できるようになっています。
派遣社員も正社員もまだ、男性の育児休暇についてあまりよく思っていないところも多いようですが、最近はさまざまな会社で認められ始めています。
どうせ男は認められないと諦めてしまう前に、派遣会社に相談してみましょう。
産休・育休が取れない会社は違法?
産休や育休が取れない会社は違法なのかどうかについて、情報をまとめました。
自分が所属しているまたは、所属する会社が信頼できる企業であるかどうかの指標ともなるでしょう。
派遣先も派遣会社も産休に対応する義務がある
条件を満たしているにも関わらず、産休・育休の拒否を派遣会社が行った場合、罰則として以下が課せられることになります。
- 報告の要請や勧告
- 企業名の公表
- 20万円以下の罰金
そのため派遣会社や派遣先には育休や産休を認める義務があります。
育休が取れなかったら実際は泣き寝入りがほとんど
産休については派遣社員へ強制をしなければいけない部分でもあるため、認める会社がほとんどですが、育休については、なかなか認められるのが難しい側面も持っているようです。
大手派遣会社などであればしっかりと対応してくれます。
ところが、競争率の激しい会社などでは育休を申請しにくい環境となっているため、育休が取れなかったら泣き寝入りしてしまっているケースも見受けられます。
同じ派遣先復帰後の待遇はどうなる?
産休や育休については何一つ後ろめたいことがないので、派遣先に復帰したとしても本来は待遇が悪化するというようなことはありません。
ところが、未だに産休や育休に偏見を持っているような、コンプライアンスに問題のある派遣先が存在している可能性も捨てきれません。
これは、「マタニティハラスメント」というハラスメントですので、派遣会社の相談窓口への相談を行うことはもとより、内容によっては労働基準監督署に相談することも考える必要があります。
派遣の産休代替は最悪?産休代替の実態
派遣の産休代替とはどんな仕事を行うのか、基本的な内容と勤務期間、メリットやデメリットについて解説していきます。
産休代替とは
産休代替とは、産休や育休を取得するスタッフの代わりに、業務を引継ぎ、短期間契約でそのポジションの仕事を行うことを指します。
派遣社員との大きな違いは、抵触日による派遣期間の制限がない点です。
つまり派遣労働法で決められた日数を超えている場合でも、同じ職場で働けるようになっています。
派遣受入期間の制限を受けない業務(=常用雇用の代替のおそれが客観的に低い業務)
① いわゆる「26業務」((1)専門的な知識等が必要な業務、(2)特別の雇用管理が必要な業務であって、当該業務に係る労働者派
遣が労働者の職業生活の全期間にわたる能力の有効発揮及び雇用の安定に資する雇用慣行を損なわないと認められるもの)② 有期プロジェクト業務(事業の開始、縮小又は廃止等のための業務であって一定の期間内に完了するもの)
③ 日数限定業務(1か月間の就業日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数より相当程度少なく且つ10日以内のもの)
④ 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
⑤ 介護休業等を取得する労働者の業務
代替期間はどれぐらい?
産休代替の期間は、一般的に産後8週間の産休と子供が1歳になるまでの育休期間までの業務となるため、1年強の勤務時間であることが考えられます。
また育休が延長される場合の期間は、最大で1年となるため、2年間の勤務を行うこともあります。
さらに育休中に休暇を取っているスタッフが、再度妊娠した時に延長されるケースもありえるため、2年以上の長丁場になる可能性も0ではありません。
産休代替のメリット
産休代替は、抜けた穴を埋めるための人材となるため、専門的なスキルなどが必要なケースもあることから、高時給で契約してもらえる案件が多く存在しています。
即戦力として働ける実力やそれなりの責任も必要になりますが、難しい仕事も任されるやりがいもメリットとなるでしょう。
期間限定で働くことで時間に余裕を持つことができるため、プライベートな時間も大切にしたいという方に、おすすめできる働き方だといえるでしょう。
産休代替のデメリット
産休代替のデメリットは、産休を取っているスタッフの体調に左右されるところにあります。
当初予定していた出産よりも時間がかかってしまって、代替の期間が延長されてしまうこともあるので、ある程度日程に余裕がないと、予定していたことを大幅に変更せざるを得ないことにもなりかねません。
またあまり詳しくない仕事を選んでしまうと、 業務がうまく進まずストレスを抱えたり、他の従業員からのサポートが必要になったりするため、短い間での人間関係構築が苦手だという方にとってはデメリットになりえます。
大手派遣会社の産休
派遣会社の産休によって、それぞれに異なる場合もあるため、大手派遣会社の産休制度について、いくつか紹介していきます。
派遣会社ではどのような産休が用意されているのか、具体的にイメージしやすくなるでしょう。
※こちら「大手派遣会社の産休」の内容に関しましては、#就職しよう編集部による執筆となり、「監修対象外」となりますのでご容赦ください。
テンプスタッフの産休
テンプスタッフには、以下のような制度などが設けられています。
- 産前6週、産後8週の産前産後休業を取得できる「産前産後休業制度」
- 子が1歳に達する日までの育児休業と、2歳まで延長可能な「育児休業制度」
リクルートスタッフィングの産休
リクルートスタッフィングでは詳しい記載はありませんでしたが、育休を取得したスタッフが復帰しやすいような環境を整える、「育休復帰サポート」が用意されています。
育休復帰サポートを使えば具体的な相談もできるので、お困りの際は相談してみましょう。
パソナの産休
パソナでは、以下の2つが用意されています。詳しい条件については参考ページにてご確認ください。
- 雇用契約期間中の42日から産後56日までの「産休期間」
- 産後57日から子供が1歳の誕生日前日まで、または最大2年延長できる「育児休暇」
アデコの産休
アデコの産休についての詳しい記載はありませんでしたが、産休への対応はもちろんのこと、ベビー用品などの特別割引や、保健師や保育士などによる育児相談など、育児支援サービスが充実しています。
その他にもベビーシッターや保育施設、病児体育など民間企業や財団法人と連帯して、利用料金や入会金の割引といったサービスが用意されています。
マンパワーの産休
マンパワーの産休取得やママサポートなどについて、詳しい内容の記載は確認できませんでした。
しかしながら、マンパワーは「マンパワーグループ クラブオフ」という登録者限定の福利厚生サービスをもっています。
その福利厚生サービスのなかには、女性支援メニューの優待なども含まれているため、産休や育休中に活用することもできます。
スタッフサービスの産休
スタッフサービスの産休についての詳しい記載はありませんでしたが、基本的な産休を取得するための条件を満たしていれば、対応してもらえるでしょう。
マイナビスタッフの産休
マイナビスタッフには、産休や育休についての詳しい記載はなく、育児に関する福利厚生なども調査時点では確認ができません。
そのため、マイナビスタッフで育休産休の取得を希望したい方は、登録時に前もって担当アドバイザーに相談しておくことをおすすめします。
ランスタッドの産休
ランスタッドでは、以下のような制度が用意されています。
- 出産予定または出産後について、所定日数の休暇が得られる「産前休暇」と「産後休暇」
- 満1歳未満の子供がいるスタッフを対象に、満1歳の誕生日前までの「育児休業」
詳しい条件や延長などについては記載されていなかったため、直接お問い合わせしてみることをおすすめします。
まとめ
今回の記事をまとめると、
派遣社員も条件を満たしていれば 育休と産休は取れる
派遣社員であったとしても、労働基準法で育休と産休は取得できる決まりとなっているため、遠慮なく派遣会社に伝えて対応してもらうようにしましょう。
もし派遣会社に相談しても相手にされなかった場合は、弁護士などへの相談も考えていきましょう。
育休と産休後でも現場復帰できる
産休と育休を属することを理由に、更新予定のあった契約を打ち切ったり、退職させたりすることは禁止されています。
信頼できる派遣会社であれば、同じ職場での復帰を目指してサポートしてくれるので、派遣会社に登録する前に、どのような対応をしてくれるのか聞いておくことをおすすめします。

代表 岡崎 壮史
社会保険労務士・1級FP技能士・CFP
マネーライフワークス代表/法人・個人事業主の助成金の申請代行、労働に関する研修講師を中心に、お金に関する記事の執筆・記事監修、社労士やFPなどの各種資格試験の受験指導の講師として多岐にわたり活躍。
マネーライフワークス
最初にチェック!
おすすめ派遣会社「スタッフサービス」
業界最大級の求人数!幅広い職種対応!
スタッフサービスは、事務やコールセンターなど幅広い職種に対応した業界大手の派遣会社です。
豊富な求人数と実績から、派遣で働きたい方の希望に合った派遣求人を紹介しています。派遣会社を探すなら、まずは「スタッフサービス」に登録することをおすすめします。